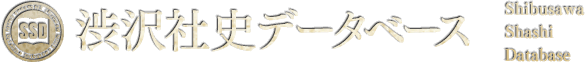目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 創立70年史刊行に際して 取締役社長 佐々田鎮正 | NP | |
|---|---|---|
| 行幸記念碑 | 巻頭 | |
| 現役員 | 巻頭 | |
| 沿革 | 巻頭 | |
| 1 てん菜糖業の挫折と再興 戦前 | p17 | |
| てん菜糖業の起源 | p17 | |
| 明治時代のてん菜糖業 | p17 | |
| 当社の前身―北海道製糖(株)、(旧)日本甜菜製糖(株)の誕生 | p17 | |
| 北海道に根づくてん菜糖業 | p17 | |
| 3工場の統合で1社に | p17 | |
| 子会社と副業部門 | p17 | |
| 2 荒廃から復興へ 昭和20年代 | p23 | |
| 日本甜菜製糖株式会社の発足 | p23 | |
| てん菜生産振興臨時措置法の成立 | p23 | |
| 原料確保のための苦闘 | p23 | |
| 戦後改革の嵐のなかで | p23 | |
| 労働組合の誕生 | p23 | |
| 新しい事業分野への進出 | p23 | |
| 3 てん菜糖業への他社参入と粗糖の輸入自由化 昭和30年代 | p28 | |
| 新規各社のてん菜糖業への参入 | p28 | |
| 美幌工場の建設 | p28 | |
| 納付金法の制定 | p28 | |
| 増産担当地域の指定と取り消し | p28 | |
| 粗糖の輸入自由化 | p28 | |
| 甘味資源特別措置法の成立 | p28 | |
| 紙筒の発明 | p28 | |
| ヨーロッパ系倍数体品種の登場 | p28 | |
| 配合飼料事業への進出 | p28 | |
| 本社移転と上白糖の製造 | p28 | |
| 日本ビート糖業協会の設立 | p28 | |
| 昭和30年代の当社の経営状況 | p28 | |
| 4 精糖業界の構造的不況と市場の混乱 昭和40年代 | p36 | |
| 深刻な不況下の精糖業界 | p36 | |
| 糖安法の制定と北海道糖業(株)の発足 | p36 | |
| 士別工場の増強と紙筒新工場の建設 | p36 | |
| 芽室工場の建設と磯分内工場の売却 | p36 | |
| 糖分取引をめぐる模索 | p36 | |
| 精製糖の輸入自由化 | p36 | |
| 国際糖価の暴騰と砂糖パニック | p36 | |
| 日豪砂糖協定の締結 | p36 | |
| 事業団への売買差額納付 | p36 | |
| 奨励金の取り扱い | p36 | |
| 単胚種子の普及 | p36 | |
| 紙筒部と農業機材部の新設 | p36 | |
| 海外関連会社の設立 | p36 | |
| ラフィノース分解装置の設置 | p36 | |
| 除土積上機の開発 | p36 | |
| 副業部門の発展 | p36 | |
| 昭和40年代の十勝鉄道(株)とズズラン企業(株)の設立 | p36 | |
| 5 てん菜作付面積の急減、そして抑制へ 昭和50年代 | p49 | |
| 貿易黒字と国家財政の悪化 | p49 | |
| 内外糖価の暴落 | p49 | |
| 大幅な減反とその対策 | p49 | |
| 砂糖売戻し特例法の施行 | p49 | |
| 過剰設備廃棄の試み | p49 | |
| 糖安法改正と構造改善 | p49 | |
| てん菜作付面積の累増と作付面積指標の設定 | p49 | |
| 歩留まりの上昇と販売の新局面 | p49 | |
| 異性化糖の急増 | p49 | |
| 糖分取引の検討 | p49 | |
| 芽室工場と帯広工場の統合 | p49 | |
| 濃厚汁製糖法 | p49 | |
| 帯広工場の閉鎖 | p49 | |
| ペレット種子の登場 | p49 | |
| ニッテンピートとマイタケ | p49 | |
| 開発部の新設とゴルフ練習場 | p49 | |
| OAとFA | p49 | |
| 総合研究所の発足 | p49 | |
| 競争激化の配合飼料事業 | p49 | |
| 需要の多様化するイースト事業 | p49 | |
| 発展をつづける紙筒事業 | p49 | |
| 転機をむかえた農業機材事業 | p49 | |
| 財務体質の改善 | p49 | |
| 昭和50年代の十勝鉄道(株)とスズラン企業(株) | p49 | |
| 6 新しい取引制度のもとで 最近の4年間 | p68 | |
| 円高と農産物の自由化 | p68 | |
| 糖分取引への準備 | p68 | |
| 糖分取引の実施 | p68 | |
| 芽室農務部門の移転 | p68 | |
| 新しい病害―そう根病 | p68 | |
| 高糖分品種の優良品種認定 | p68 | |
| ペレット種子工場と種子精選工場の建設 | p68 | |
| 産構法下での砂糖市況 | p68 | |
| 子会社、(株)プランテク・ニッテンの設立 | p68 | |
| 副業部門の合理化 | p68 | |
| 十勝鉄道(株)とスズラン企業(株)の近況 | p68 | |
| 結び | p78 | |
| 資料 | p81 | |
| 年表 | p95 | |
| 編集後記 | NP |
- 索引リスト
-