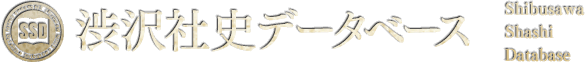目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 口絵 | 巻頭 | |
|---|---|---|
| 発刊の辞 | NP | |
| 百年史の刊行に寄せて | NP | |
| 目次 | NP | |
| 凡例 | NP | |
| 百年史のあらまし | NP | |
| 第1編 ハンター、範多父子経営時代(明治14年から大正3年まで) | p3 | |
| 第1章 E.H.ハンターによる経営(明治14年から明治28年まで) | p3 | |
| 第1節 大阪鉄工所の創業と苦難 | p3 | |
| 1. 創業まで | p3 | |
| 近代造船業の夜明け | p3 | |
| 開港・開市とロンドン覚書 | p4 | |
| キルビー、ハンターの関西入り | p5 | |
| E.H.ハンターの独立 | p6 | |
| 造船所は政府直営で整備 | p7 | |
| 紙幣整理と官業払い下げ | p7 | |
| 民間造船業始まる | p7 | |
| 西南戦争後のハンター | p8 | |
| 2. 創業 | p9 | |
| 大阪鉄工所の創立 | p9 | |
| 大阪鉄工所の創業 | p10 | |
| 3. 創業当時の業容 | p10 | |
| イギリス領事の報告書 | p10 | |
| 新造1番船初丸 | p11 | |
| 表面凝縮連成冷気機関の製造 | p11 | |
| 陸上用機関の製造 | p11 | |
| 鉄船修繕工事の開始 | p11 | |
| 4. 事業のつまずき | p12 | |
| 西南戦争後の不況 | p12 | |
| 資金難に陥る | p12 | |
| 事業の譲渡と復帰 | p13 | |
| 第2節 事業基盤の確立 | p14 | |
| 1. 明治初期の海運業界 | p14 | |
| 維新政府の海運政策 | p14 | |
| 日本国郵便蒸気船会社の新設 | p14 | |
| 郵便汽船三菱会社の奮闘 | p14 | |
| 日本郵船会社の誕生 | p15 | |
| 阪神の海運業界 | p15 | |
| 大阪商船会社の設立 | p17 | |
| 2. 事業の再建と施設の拡充 | p17 | |
| 淀川丸の建造から再建の軌道へ | p17 | |
| 外国人技術者の退職 | p18 | |
| 邦人技術者の入所 | p18 | |
| ハンターの日本人に対する信頼 | p18 | |
| ドックの改築及び本部事務所の建設 | p19 | |
| 木船工場の開設 | p19 | |
| 3. 新技術に挑む | p19 | |
| 鉄船の建造 | p19 | |
| 浚渫船で苦汁をなめる | p20 | |
| 鋼船の建造 | p20 | |
| 消防艇の建造 | p21 | |
| 三連成機関の製造 | p21 | |
| (認許手続きでひと苦労) | p22 | |
| 浅吃水船の建造が役立つ | p22 | |
| 運炭船専用曳船の建造 | p23 | |
| 4. 日清戦争による繁忙 | p23 | |
| 軍用船舶の修繕 | p23 | |
| 海軍用小汽艇の建造 | p24 | |
| 陸軍検疫所の汽機製作及び建設工事 | p24 | |
| 陸上用機械の需要増 | p24 | |
| 5. 事業の基礎固まる | p25 | |
| 創業時の職制と精神的結合 | p25 | |
| 業績の向上 | p25 | |
| 第2章 範多竜太郎による経営(明治28年から大正3年まで) | p27 | |
| 第1節 日清戦争後の発展 | p27 | |
| 1. 経営の継承 | p27 | |
| E.H.ハンターから範多竜太郎へ | p27 | |
| 職制と人事の刷新 | p28 | |
| 2. 浚渫船工事の開始 | p28 | |
| 浚渫事業の重要度増す | p28 | |
| パケット式浚渫船の建造 | p28 | |
| 大阪築港工事に寄与 | p29 | |
| 大阪築港用特殊船の建造並びに陸上機械の製作 | p30 | |
| 浚渫船研究の成果 | p30 | |
| 3. 海運・造船保護政策の確立 | p31 | |
| 日清戦争の造船・海運業界への影響 | p31 | |
| 造船奨励法・航海奨励法及び関税定率法の制定 | p31 | |
| 造船奨励法による造船業界の活況 | p32 | |
| 4. 桜島造船場の建設と航洋船の建造開始並びに浅喫水船及び水管汽缶の開発 | p32 | |
| 桜島造船場の建設 | p32 | |
| 造船奨励法適格航洋船第1船の建造 | p34 | |
| 大型浅喫水船の建造 | p34 | |
| 小型浅喫水船の研究とその成果 | p34 | |
| 山木式水管汽缶の開発と蛟龍丸 | p35 | |
| 5. 陸上関係工事の開拓 | p36 | |
| 鋳鉄管事業の開拓 | p36 | |
| 橋梁製作の開始 | p36 | |
| 海事工業も手掛ける | p37 | |
| 6. 台湾への進出 | p37 | |
| 台湾進出の経緯 | p37 | |
| 基隆分工場の開設 | p37 | |
| 7. 個人経営時代の労務の状況 | p38 | |
| 明治33年の年齢構成並びに賃金事情 | p38 | |
| 労働事情 | p39 | |
| 8. 受賞と栄誉 | p39 | |
| 第5回内国勧業博覧会に出品 | p39 | |
| 侍従の派遣を受ける | p40 | |
| 第2節 日露戦争以後の企業規模の拡大 | p42 | |
| 1. 日露戦争による繁忙 | p42 | |
| 日露戦争の海運・造船業界に与えた影響 | p42 | |
| 軍用艦艇の建造 | p42 | |
| 戦時貨客船の建造 | p43 | |
| 2. 日露戦争後の不況対策 | p44 | |
| 戦後の経済変動 | p44 | |
| 造船業界の不況 | p44 | |
| 当所の不況対策 | p45 | |
| 沖合遠洋漁業の発達 | p45 | |
| 捕鯨船の建造 | p45 | |
| 捕鯨母船の研究 | p46 | |
| アメリカ式捕鯨船の建造 | p46 | |
| トロール漁船の開発 | p46 | |
| 冷蔵装置付き漁獲物処理運搬船及び流網漁船の開発 | p47 | |
| 浚渫船及び起重機船の建造 | p47 | |
| その他の特殊船の開発 | p48 | |
| 陸上関係工事の開発増強 | p49 | |
| 3. 施設の拡充 | p49 | |
| 天保山分工場の開設 | p49 | |
| 安治川本工場の拡充 | p51 | |
| 尼崎鋳管工場の建設 | p51 | |
| 東京連絡所の設置 | p51 | |
| 4. 造船・航海両奨励法の改廃と当所の対策 | p51 | |
| 造船奨励法の改正 | p51 | |
| 遠洋航路補助法の制定並びに関税定率法の改正 | p52 | |
| 改正奨励法・補助法に対する当所の対策 | p52 | |
| 因島分工場の開設とその意義 | p53 | |
| 大型船の受注と建造 | p53 | |
| 北京丸・南京丸建造の意義 | p54 | |
| イシャーウッドとの粘り強い交渉 | p54 | |
| 鋼材輸入の便利さ | p55 | |
| 5. 個人経営時代の終結 | p55 | |
| 業界における当所の地位 | p55 | |
| 当所の経営環境 | p56 | |
| 株式会社への組織変更 | p56 | |
| 株式会社設立の辞 | p57 | |
| 大正3年3月末の財務状態 | p57 | |
| 大正3年3月末の人員並びに個人経営時代の製品 | p59 | |
| 第2編 株式会社大阪鉄工所時代(大正3年から昭和20年終戦まで) | p63 | |
| 第1章 大阪商船系による経営(大正3年から大正7年まで) | p63 | |
| 第1節 株式会社大阪鉄工所の発足 | p63 | |
| 1. 株式会社大阪鉄工所の設立 | p63 | |
| 設立 | p63 | |
| 株式会社大阪鉄工所の客観的評価 | p64 | |
| 組織と人事 | p65 | |
| 山岡社長の訓示 | p65 | |
| 2. 設立当初の業容 | p66 | |
| 施設の拡充 | p66 | |
| 第1次世界大戦の勃発 | p67 | |
| 大戦勃発時の当社の状況 | p67 | |
| 桜島工場の栄誉 | p67 | |
| 桜島ドックの完成 | p68 | |
| 山岡社長の会長就任 | p68 | |
| 大正3年の受注状況 | p68 | |
| 大正3年の新造船建造状況 | p68 | |
| 駆逐艦杉の建造 | p69 | |
| 大正4年の新造船建造状況 | p69 | |
| 大正4年の受注急増 | p70 | |
| 第2節 第1次世界大戦と事業の拡大 | p71 | |
| 1. 工場施設の拡充 | p71 | |
| 世界的船腹の不足 | p71 | |
| 山岡会長の積極的経営方針 | p71 | |
| 臨時建築部の設置 | p72 | |
| 第1期拡張工事 | p72 | |
| 第2期拡張工事 | p73 | |
| 因島工場の新造船への進出 | p73 | |
| 増資と社債の発行 | p74 | |
| 工場の集約合理化 | p74 | |
| 尼崎工場の譲渡 | p74 | |
| 基隆工場の閉鎖 | p74 | |
| 本社と安治川工場の桜島移転集中 | p75 | |
| E.H.ハンター翁銅像の建立 | p75 | |
| 範多氏職工奨励基金の設定 | p76 | |
| 2. 第1次世界大戦による繁忙 | p76 | |
| 貨物船需要の著増 | p76 | |
| 大正5・6年の新造船とイシャーウッド式船体構造船 | p77 | |
| 仕入船建造計画の不要 | p77 | |
| (イシャーウッド式船体構造船の建造量) | p77 | |
| (日本汽船と当社との関係) | p78 | |
| (日本汽船発足の経緯) | p78 | |
| 3. 日米船鉄交換史 | p78 | |
| 4. 技術の導入並びに横卸し進水の実施 | p83 | |
| タービンの製造権取得 | p83 | |
| ガス溶断・溶接の導入 | p84 | |
| 安南丸の横卸し進水 | p85 | |
| 5. 労務施策 | p86 | |
| 従業員の増加 | p86 | |
| 職工規程の制定 | p86 | |
| 職工共済会の設立 | p87 | |
| 因島病院の開設 | p87 | |
| 第2章 大阪商船・久原両系による経営(大正7年から大正15年まで) | p89 | |
| 第1節 経営陣の交代 | p89 | |
| 1. 久原系資本の進出 | p89 | |
| 範多家資本の後退 | p89 | |
| 増資と久原系資本の進出 | p90 | |
| 2. 経営陣の交代 | p90 | |
| 大阪商船・久原両系の経営陣 | p90 | |
| 日本汽船の当社株式取得 | p90 | |
| (久原の大工業都市計画と中止時における当社の協力) | p91 | |
| 第2節 第1次世界大戦末期の躍進と大戦終結対策 | p92 | |
| 1. 海運・造船業界の発展 | p92 | |
| 海運業界の好況 | p92 | |
| 造船業界の躍進 | p93 | |
| 関連機械工業の成長 | p93 | |
| 2. 業績の躍進と大戦終結に伴う対策 | p94 | |
| 造船奨励法の廃止と当社の同法適格船建造量 | p94 | |
| 船型の標準化・大型化 | p94 | |
| 大正7年の記録的新造船建造 | p94 | |
| 大戦後の不況に備えて | p95 | |
| 大正7年末の新造船手持工事量 | p95 | |
| 大正8年の新造船対策 | p96 | |
| 大正9年の需要急減と新造船建造状況 | p96 | |
| 3. 施設の拡充 | p97 | |
| 本社の移転 | p97 | |
| 拡張工事の継続 | p97 | |
| 備後工場の開設 | p99 | |
| 4. 労務施策 | p99 | |
| 利益標準奨励金制度の実施 | p99 | |
| 8時間労働制の実施 | p99 | |
| 第3節 第1次大戦後不況の克服 | p100 | |
| 1. 海運・造船業界の衰微 | p100 | |
| 大活況の名残と大不況の到来 | p100 | |
| 海運業界の衰微 | p100 | |
| 造船業界の衰微 | p101 | |
| ワシントン軍縮条約による追い打ち | p101 | |
| 2. 大戦後不況下の新造船並びに当社海運部門の消長 | p102 | |
| 手持工事量の激減 | p102 | |
| 貨物船建造の減少 | p102 | |
| 貨客船建造の再開 | p102 | |
| 艦艇の建造 | p103 | |
| 大型トロール船の建造と漁船のディーゼル化 | p103 | |
| 浚渫船・起重機船の建造 | p104 | |
| 特殊就役船の建造 | p104 | |
| ディーゼル貨客船の建造 | p105 | |
| 電気推進船の建造 | p105 | |
| (久原商事の窮迫による日本汽船の整理) | p105 | |
| (久原の商事部門進出の経緯並びに当社との関係) | p106 | |
| 当社海運部門の消長 | p107 | |
| 3. 技術の導入 | p108 | |
| 電気溶接の導入 | p108 | |
| ディーゼル並びにタービンの研究 | p108 | |
| 4. 施設の増強 | p109 | |
| 船舶修繕能力の増大 | p109 | |
| 築港工場の開設 | p109 | |
| 関係会社の設立 | p110 | |
| 天保山工場の返還 | p110 | |
| 彦島工場の開設 | p110 | |
| 笠戸島工場の経営受託 | p110 | |
| 本社の移転 | p111 | |
| 5. 修繕船工事の増加並びに陸上関係工事への進出 | p111 | |
| 修繕船工事の飛躍的増加 | p111 | |
| 陸上関係工事への進出 | p111 | |
| 車両工事の再開 | p111 | |
| 橋梁工事の再開 | p112 | |
| 諸機械その他の製作 | p113 | |
| 6. 労働事情 | p114 | |
| ワシントン軍縮会議の影響 | p114 | |
| 労働争議の発生 | p115 | |
| 職工規程の改正と退職慰労金 | p115 | |
| 7. 経営陣の交代 | p116 | |
| 大阪商船・久原両系による経営の終結 | p116 | |
| 大正時代の業績の推移 | p116 | |
| 第3章 久原系による経営(大正15年から昭和7年まで) | p119 | |
| 第1節 経営環境の悪化並びに経営方針の更新 | p119 | |
| 1. 世界恐慌と海運・造船業界 | p119 | |
| 世界恐慌 | p119 | |
| 日本の長期不況とその深刻化 | p120 | |
| 海運・造船業界の不況 | p120 | |
| 2. 経営方針の更新 | p121 | |
| 津村会長・飯島支配人体制 | p121 | |
| 経営方針の更新 | p121 | |
| 第2節 恐慌下の経営 | p122 | |
| 1. 経営の改革 | p122 | |
| 経費の節減と会計上の改革 | p122 | |
| 工事監査員制度の実施と工場管理課の新設 | p123 | |
| 海軍省からの艦艇受注、因島・桜島両工場の栄誉 | p123 | |
| 日本郵船からの受注 | p124 | |
| 鉄道省の指定工場受認と橋輌課の新設 | p125 | |
| 営業並びに本社工場の組織強化 | p125 | |
| 2. 製品の多角化並びに技術力の向上 | p125 | |
| 新造船工事量の不足 | p125 | |
| 新造船の不振 | p126 | |
| 平洋丸・平安丸の河川進水記録 | p129 | |
| 修繕船受注競争の激化 | p130 | |
| 向島船渠への経営参加 | p131 | |
| 車両製作の伸長 | p132 | |
| 橋梁工事の増加 | p132 | |
| 鉄骨・鉄塔・鉄柱・屋外鉄構工事の増加 | p132 | |
| 水圧鉄管・水門・貯槽工事の増加 | p136 | |
| 化学工業用諸機器の製作並びに据付工事 | p136 | |
| (太田橋のケーブルによる架設) | p140 | |
| (長岡市上水道用水槽塔工事) | p140 | |
| (堂島川可動堰工事) | p140 | |
| 3. 桜島工場の火災並びに労務施策の充実 | p141 | |
| 桜島工場の火災 | p141 | |
| 労務施策の画期的な充実 | p141 | |
| 4. 日産系の経営へ | p145 | |
| 日本産業株式会社への株式移動 | p145 | |
| 久原系による経営の終結 | p146 | |
| (日産コンツェルンの概要) | p147 | |
| 第4章 日本産業株式会社傘下の経営(昭和7年から昭和11年まで) | p151 | |
| 第1節 株式会社日本産業大阪鉄工所の設立経過 | p151 | |
| 1. 鮎川会長・原田社長体制 | p151 | |
| 鮎川義介の会長就任 | p151 | |
| 鮎川会長・原田社長体制の確立と組織の改正 | p152 | |
| 2. 営業の概況 | p153 | |
| 経済情勢の変化と海運・造船業界の状況 | p153 | |
| 新造船などの受注状況 | p153 | |
| 新造船の建造状況 | p154 | |
| 修繕船の増加 | p155 | |
| 雄基丸等の船体引き伸ばし工事 | p155 | |
| 陸上関係工事の増加 | p156 | |
| 電気溶接技術の向上 | p157 | |
| 業績の推移 | p158 | |
| 3. 日本産業株式会社に合併 | p158 | |
| (日本産業の多角化戦略の開始) | p158 | |
| (日本産業による企業の浄化作用) | p159 | |
| (当社の日本産業への合併) | p159 | |
| 第2節 新会社としての株式会社大阪鉄工所の発足 | p161 | |
| 1. 株式会社日本産業大阪鉄工所の発足と旧社名の踏襲 | p161 | |
| 株式会社日本産業大阪鉄工所の設立 | p161 | |
| 旧社名株式会社大阪鉄工所の踏襲 | p161 | |
| 組織の変更 | p162 | |
| 桜島工場の栄誉 | p162 | |
| 2. (新)株式会社大阪鉄工所発足当初の業容 | p163 | |
| 発足時の会社の概要 | p163 | |
| 発足当初の受注環境 | p163 | |
| 大風水害とその復興 | p164 | |
| 原田社長の訓示 | p166 | |
| 原田社長の悲報 | p166 | |
| 海軍方面の関係好転 | p166 | |
| 役員構成と役員の増員 | p167 | |
| 株主数と大株主の推移 | p168 | |
| 鮎川会長の事業精神 | p168 | |
| 第5章 株式会社日立製作所傘下の経営(昭和11年から昭和20年終戦まで) | p171 | |
| 第1節 経済情勢の好転と当社の躍進 | p171 | |
| 1. 株式会社日立製作所による経営体制の確立 | p171 | |
| 株式会社日立製作所への株式移動 | p171 | |
| 小平会長・六角社長体制の確立 | p172 | |
| 六角社長の就任挨拶 | p172 | |
| 資本の増加 | p173 | |
| 2. 海運・造船業界の好況化 | p173 | |
| 船舶改善助成施設並びに船舶輸入許可規則の実施 | p173 | |
| 優秀船舶建造助成施設の実施 | p174 | |
| 遠洋・外地漁業の発展 | p175 | |
| 標準船型の選定 | p175 | |
| 3. 業績の飛躍的向上 | p175 | |
| 経営環境の変化 | p175 | |
| 純益金の倍増 | p175 | |
| 4. 船舶関係工事の繁忙 | p176 | |
| 新造船の増加 | p176 | |
| 漁船の建造 | p177 | |
| 特殊船の建造 | p179 | |
| 艦艇船の新造・修繕 | p179 | |
| 第二・第三図南丸の建造 | p180 | |
| 修繕船の激増 | p181 | |
| 第二・第三図南丸の進水記録並びにノラメルスク号の大改造 | p182 | |
| 5. 陸上関係工事の急伸 | p184 | |
| 産業機械の急伸、プラントも受注 | p184 | |
| 化学機械 | p184 | |
| 鉱山機械・採金船 | p185 | |
| 製鉄・鍛錬機 | p185 | |
| 諸機械 | p186 | |
| 内燃機関・汽機汽缶 | p186 | |
| 橋梁・鉄骨・鉄塔・鉄構 | p190 | |
| 水圧鉄管・水門・可動堰 | p191 | |
| 屋外大型貯槽 | p191 | |
| 6. 施設の拡充整備 | p192 | |
| (1) 桜島工場 | p192 | |
| 敷地と建物 | p192 | |
| 車両工事の日立製作所移管と第三機械工場 | p192 | |
| 鉄塔工場の新設 | p192 | |
| 内燃機製造工場の新設 | p193 | |
| 鍛造工場の増設 | p193 | |
| 揚錨機製作工場の新設 | p193 | |
| (2) 築港工場 | p193 | |
| 敷地と建物 | p193 | |
| 鋳鋼工場の新設 | p193 | |
| 2万トンドックの築造 | p194 | |
| (3) 因島工場 | p195 | |
| 敷地と建物 | p195 | |
| 新造船工事の再開 | p195 | |
| 3万トンドックの築造 | p195 | |
| 三庄工場の再開 | p196 | |
| 逓信局海事部出張所の開設 | p197 | |
| (4) 彦島工場 | p197 | |
| 敷地と建物 | p197 | |
| 工場施設の改善 | p197 | |
| (5) 神奈川工場の建設計画 | p197 | |
| 関東への進出 | p197 | |
| 工場建設緒に就く | p198 | |
| (6) 事務所 | p198 | |
| 本社の移転 | p198 | |
| 東京事務所 | p199 | |
| 神戸事務所 | p199 | |
| 呉出張所の開設 | p199 | |
| 7. 社業の進展と組織・制度の充実 | p199 | |
| 社業の著しい進展 | p199 | |
| 六角社長の要望 | p200 | |
| 組織の充実 | p200 | |
| 大阪鉄工所標準の制定 | p201 | |
| 社内略号の制定 | p201 | |
| 発明考案表彰規程の制定 | p201 | |
| 広報の充実 | p202 | |
| 社史・カタログの編集 | p202 | |
| 技術雑誌『大阪鉄工』の創刊 | p202 | |
| 社内誌『鉄華』の改題 | p202 | |
| 桜島工場の栄誉 | p203 | |
| 小平会長の経営観 | p203 | |
| 第2節 太平洋戦争期の業容(日立造船株式会社と社名改称) | p205 | |
| 1. 海運・造船業界の戦時体制 | p205 | |
| 海運・造船の国家管理 | p205 | |
| 計画造船の推移 | p206 | |
| 2. 施設の拡張並びに造船所別作業区分 | p207 | |
| 戦時統制下の施設拡張 | p207 | |
| 神奈川造船所の建設 | p207 | |
| 設計部の設置並びに移転 | p209 | |
| 桜島造船所の拡張 | p209 | |
| 岩中機械製作所・ミツワ製材工業の買収 | p210 | |
| 築港造船所の拡充 | p210 | |
| 因島造船所の拡充 | p210 | |
| 向島船渠・原田造船の吸収合併と向島・大浪両造船所の開設 | p211 | |
| 彦島造船所の譲渡 | p212 | |
| 協和造船株式会社の創設 | p212 | |
| 九竜造船所の経営受託 | p213 | |
| 3. 戦時中の工事 | p214 | |
| 新造船工事 | p214 | |
| 修繕船工事 | p215 | |
| 陸上関係工事 | p215 | |
| 4. 増資並びに社名の改称 | p219 | |
| 資本の増加 | p219 | |
| 配当の停止 | p219 | |
| 日立造船株式会社と社名改称 | p219 | |
| 決戦下の組織改正 | p220 | |
| 5. 教育及び福利厚生 | p220 | |
| 従業員の教育 | p220 | |
| 青年学校 | p221 | |
| 技術員養成所 | p221 | |
| 宿舎施設 | p222 | |
| 医療施設 | p223 | |
| その他の福利厚生 | p223 | |
| 6. 戦争末期の状況 | p225 | |
| 工場疎開 | p225 | |
| 戦災 | p226 | |
| 終戦 | p227 | |
| 在外資産の喪失 | p227 | |
| 第3編 日立造船株式会社の新生と発展(昭和20年終戦から昭和56年まで) | p231 | |
| 第1章 日立造船株式会社の新生と戦後復興(昭和20年終戦から昭和25年まで) ―出田社長時代― | p231 | |
| 第1節 戦後復興への歩み | p231 | |
| 1. 終戦直後の混迷 | p231 | |
| 日本経済の非軍事化と民主化 | p231 | |
| 終戦直後の海運業界 | p232 | |
| 終戦直後の造船業界 | p233 | |
| 2. 復興への歩み | p234 | |
| 計画造船始まる | p234 | |
| 政府貿易による船舶輸出 | p234 | |
| 対日政策の緩和 | p235 | |
| 第2節 日立造船株式会社の新生 | p235 | |
| 1. 再建整備 | p235 | |
| 事業の再開 | p235 | |
| 会社経理応急措置法及び企業再建整備法の公布 | p236 | |
| 集中排除の指定解除と再建整備計画 | p236 | |
| 2. 株式の公開と日立造船株式会社の新生 | p237 | |
| 当社全株式持株委へ譲渡される | p237 | |
| 公職追放による経営首脳陣の交代 | p237 | |
| 日立製作所の経営傘下からの離脱 | p237 | |
| 株式の公開と日立造船株式会社の新生 | p238 | |
| 経営27項目の発表 | p238 | |
| 再建整備計画の実行完了 | p240 | |
| 副社長制の採用 | p240 | |
| 3. 組織改正・増資・社債 | p240 | |
| 組織の拡充 | p240 | |
| 資本の増加 | p241 | |
| 社債の発行 | p241 | |
| 第3節 技術研究並びに技術提携 | p242 | |
| 1. 技術研究所の開設 | p242 | |
| 技術研究の機運 | p242 | |
| 技術研究所の開設 | p243 | |
| 2. B&W型ディーゼル機関の製造販売権取得 | p244 | |
| 戦後最初の技術導入 | p244 | |
| 当社ディーゼル機関の生産実績 | p244 | |
| B&W型ディーゼル機関の選定事情 | p244 | |
| B&W型ディーゼル機関再実施権契約の締結 | p245 | |
| 第4節 施設の復旧整備と生産の再開 | p246 | |
| 1. 施設の復旧整備 | p246 | |
| 復旧整備の開始 | p246 | |
| 桜島工場 | p246 | |
| 築港工場 | p247 | |
| 梵鐘の製作 | p248 | |
| 因島工場 | p248 | |
| 向島工場 | p249 | |
| 神奈川工場 | p249 | |
| 泉尾製材所の閉鎖 | p250 | |
| 東京事務所の移転 | p250 | |
| 神戸事務所の移転 | p250 | |
| 門司営業所の開設 | p250 | |
| 大浪工場と大浪運輸倉庫株式会社 | p250 | |
| 大淀工場と日立ミシン株式会社 | p250 | |
| 2. 生産の再開 | p252 | |
| (1) 船舶部門 | p252 | |
| 続行船から建造開始 | p252 | |
| 小型漁船・捕鯨船の建造 | p252 | |
| 1次船から4次船までの受注と輸出指向 | p252 | |
| 5次船で当社最大の受注 | p253 | |
| 修繕・改造・解撤工事 | p253 | |
| 橋立丸の改造 | p254 | |
| せりあ丸の改造 | p254 | |
| その他の改造船 | p255 | |
| (2) 陸機部門 | p256 | |
| 化学肥料装置から製作開始 | p256 | |
| 合成繊維機器の製作 | p256 | |
| 製塩装置を手掛ける | p256 | |
| 橋梁・水門の製作開始 | p257 | |
| 鉄骨・その他の工事 | p257 | |
| (3) 政府貿易による輸出工事 | p257 | |
| フィリピン向け製紙機械 | p257 | |
| ノルウェー向け捕鯨船 | p258 | |
| ソ連貨物船の改造 | p258 | |
| 第5節 終戦直後の労務状況 | p258 | |
| 1. 従業員の状況 | p258 | |
| 在籍者数の推移 | p258 | |
| 社工員制及び係長制の実施 | p259 | |
| 賃金の上昇 | p259 | |
| 2. 労使関係 | p259 | |
| 労働組合の結成 | p259 | |
| 労働協約の締結 | p260 | |
| 桜島労組のデモ | p260 | |
| 3. 福祉対策 | p261 | |
| 住宅難対策 | p261 | |
| 医療対策 | p261 | |
| 第2章 松原社長時代の経営 その1(昭和25年から昭和30年まで) ―復興整備期― | p263 | |
| 第1節 新生日立造船株式会社の基礎固め | p263 | |
| 1. 造船業の本格的な復興 | p263 | |
| 朝鮮動乱による外航船不足と輸出船 | p263 | |
| 昭和29年不況 | p264 | |
| 粗糖リンク制による輸出助成と第1次輸出船ブーム | p265 | |
| 2. 硝子張りの中の経営、人間尊重の経営を進める | p267 | |
| 経営陣の強化 | p267 | |
| 松原社長の輸出重点及び労使協調の2大方針 | p267 | |
| 年頭巡視で従業員と懇談 | p268 | |
| 安全運動の推進 | p269 | |
| 社是の制定 | p270 | |
| 海運造船疑獄事件と労働組合 | p270 | |
| 3. 組織改正・増資・社債 | p272 | |
| 営業部門の拡充 | p272 | |
| 資本の増加 | p272 | |
| 社債の発行 | p272 | |
| 第2節 技術研究並びに日立B&Wディーゼル機関の製造開始 | p273 | |
| 1. 技術研究所軌道に乗る | p273 | |
| 初期の研究 | p273 | |
| 戦後初の海外技術視察 | p275 | |
| 2. 日立B&Wディーゼル機関の製造開始 | p275 | |
| 1番機の製造 | p275 | |
| 日立B&Wディーゼル機関製造の意義 | p276 | |
| ライセンシー会議に出席 | p276 | |
| アルファ型機関の製造 | p276 | |
| 製造開始後5年間の製造実績 | p277 | |
| 第3節 工場整備5か年計画の実施並びに本社の移転 | p278 | |
| 1. 復興整備計画と近代化・合理化 | p278 | |
| 2. 桜島工場 | p278 | |
| 整備5か年計画の実施 | p278 | |
| 防潮岸壁の完成 | p279 | |
| ディーゼル機関生産設備の拡充 | p279 | |
| 特別高圧受電設備の完成 | p279 | |
| 桜島会館の建設 | p279 | |
| その他の施設 | p280 | |
| 3. 築港工場 | p280 | |
| 整備5か年計画の実施 | p280 | |
| 4. ジェーン台風による被害 | p281 | |
| 桜島工場 | p281 | |
| 築港工場 | p281 | |
| 5. 因島工場 | p283 | |
| 整備5か年計画の実施 | p283 | |
| 造船設備の大拡張 | p285 | |
| 6. 向島工場 | p285 | |
| 整備5か年計画の実施 | p285 | |
| 7. 神奈川工場 | p286 | |
| 整備5か年計画の実施 | p286 | |
| 木造舟艇工場 | p287 | |
| 8. 本社の移転 | p287 | |
| 第4節 復興に伴う業績の回復進展 | p289 | |
| 1. 国内新造船 | p289 | |
| 6次船から溶接法を全面採用 | p289 | |
| 高速船の開発 | p289 | |
| 10次船の試錬 | p290 | |
| 漁船・捕鯨船・冷凍工船の建造 | p290 | |
| 木造舟艇の建造 | p291 | |
| その他の新造船 | p291 | |
| 2. 改造船・修繕船 | p291 | |
| 外国船級取得工事の著増 | p291 | |
| 船体引き伸ばし工事 | p292 | |
| その他の改造船 | p292 | |
| 3. 産業機械 | p294 | |
| 化学肥料装置 | p294 | |
| 合成繊維・合成樹脂機器 | p294 | |
| パルプ製造装置 | p295 | |
| セメント機器 | p295 | |
| その他各種産業機械 | p295 | |
| 4. 国内鉄構 | p297 | |
| 橋梁 | p297 | |
| 鉄骨 | p297 | |
| 鉄塔・屋外鉄構 | p298 | |
| 水門 | p298 | |
| 水圧鉄管・水道鋼管 | p299 | |
| タンク工事 | p299 | |
| 第5節 海外市場の開拓に社運を賭ける(輸出のパイオニアへの道) | p302 | |
| 1. 輸出船の受注 | p302 | |
| アメリカから民間貿易初のタンカー受注 | p302 | |
| インドネシアから巡礼船受注 | p303 | |
| ソ連から曳船・漁船受注 | p304 | |
| 輸出船の大量受注 | p304 | |
| 2. プラント・鉄構の受注 | p304 | |
| ビルマから砂糖プラント受注 | p304 | |
| 発電所用鉄構受注 | p305 | |
| 3. 海外活動の積極化 | p305 | |
| 海外渡航者・海外駐在員の派遣 | p305 | |
| 新年パーティの開始 | p306 | |
| 海外向け広告の開始 | p306 | |
| 第6節 労務の状況 | p307 | |
| 1. 教育 | p307 | |
| 社長宣言と従業員教育諸規程の制定 | p307 | |
| 教育の実施 | p307 | |
| 2. 労使関係正常化への生みの悩み | p308 | |
| 総合的労働協約の締結から予備協定締結へ | p308 | |
| 特別整理 | p309 | |
| 戦後初めての争議発生 | p309 | |
| 昭和29年不況下の労使関係 | p310 | |
| ロレ内部対立が表面化 | p310 | |
| 3. 衛生管理 | p311 | |
| 衛生管理 | p311 | |
| 健康保険組合の活動 | p311 | |
| 第7節 事務管理・資材管理・70周年記念事業 | p312 | |
| 1. 事務管理 | p312 | |
| 社内用紙規格の統一 | p312 | |
| 制度調査委員会による事務改善 | p312 | |
| 大型計算機械の導入 | p313 | |
| 2. 資材管理 | p313 | |
| 資材の集中購買制度の確立 | p313 | |
| 3. 70周年記念事業 | p314 | |
| 式典と永年勤続者表彰 | p314 | |
| 社史編集と社歌制定 | p314 | |
| 『日立造船社報』の復刊 | p314 | |
| 第3章 松原社長時代の経営 その2(昭和30年から昭和37年まで) ―拡充成長期― | p315 | |
| 第1節 日本経済の高度成長 | p315 | |
| 1. 高度成長の展開 | p315 | |
| 日本経済の近代化と高度成長 | p315 | |
| 外国技術の導入 | p316 | |
| コンビナートの建設 | p317 | |
| 2. 造船業界の発展 | p319 | |
| 我が国造船量世界首位に | p319 | |
| 陸上部門への進出 | p320 | |
| 自己資金船建造の増加 | p321 | |
| 船舶の大型化・専用化・自動化・高速化 | p321 | |
| 第2節 経営体制の強化 | p323 | |
| 1. 経営方針の明確化と社格向上の推進 | p323 | |
| 年頭指針の全社的推進 | p323 | |
| 調査・広報活動の重視 | p323 | |
| 2. 輸出体制の確立 | p324 | |
| 輸出営業組織の拡充整備 | p324 | |
| 海外事務所の開設とアフターサービス事務所の開設 | p325 | |
| 3. 技術力の強化 | p326 | |
| 生産技術の総合的向上を志向 | p326 | |
| 設計部門の拡充強化 | p326 | |
| 技術革新時代に対処 | p327 | |
| 新製品開発体制の強化 | p327 | |
| 4. 総合重機械工業を志向 | p328 | |
| 桜島工場を陸機の主力工場に | p328 | |
| 日立造船エンジニアリング株式会社の設立 | p329 | |
| 陸機部門の増強 | p329 | |
| 技術導入の積極化 | p330 | |
| 5. 船舶の大型化に対処 | p331 | |
| 因島工場を造船の主力工場に | p331 | |
| 堺に新工場の建設決定 | p332 | |
| 6. 増資 | p333 | |
| 資本の増加 | p333 | |
| 第3節 受注と生産 | p334 | |
| 1. 国内船 | p334 | |
| 計画造船受注の推移 | p334 | |
| 自己資金船と新会社の設立 | p335 | |
| 艦艇 | p336 | |
| 特殊船その他 | p337 | |
| (浚渫船) | p337 | |
| (漁船) | p337 | |
| (舟艇) | p337 | |
| (消防艇) | p337 | |
| (客船) | p338 | |
| 2. 輸出船 | p338 | |
| 新市場の開拓 | p338 | |
| ソ連から大量受注 | p340 | |
| メジャーオイルからの受注 | p340 | |
| 3. 建造量の増大と高性能船の建造 | p341 | |
| 建造量の増大と輸出比率の拡大 | p341 | |
| 建造船の大型化・専用化 | p342 | |
| (大型化) | p342 | |
| (専用船化) | p343 | |
| (自動化) | p345 | |
| (高速化) | p345 | |
| 水中翼船の建船開始 | p346 | |
| 4. 修繕船 | p347 | |
| 修繕船工事実績、業界の首位に | p347 | |
| 経営の安定に貢献 | p348 | |
| 改造船工事相次ぐ | p348 | |
| 5. 日立B&Wディーゼル機関 | p349 | |
| 創業75周年記念式典にメッセージ | p349 | |
| B&W社と直接契約へ | p350 | |
| 世界最大1万5,000馬力機関の完成 | p350 | |
| 世界最初の高過給大型機関の完成 | p351 | |
| 6. 産業機械 | p352 | |
| パルプ製造装置 | p352 | |
| 化学・石油化学製品製造装置 | p353 | |
| 製鉄機械 | p354 | |
| プレス | p355 | |
| 食品機械 | p356 | |
| 7. 鉄鋼構造物 | p357 | |
| 橋梁 | p357 | |
| 水門 | p359 | |
| 水圧鉄管・水道鋼管 | p360 | |
| 鋼製煙突 | p361 | |
| 鉄骨・鉄塔・貯槽 | p361 | |
| 8. 輸出貢献企業表彰を受ける | p363 | |
| 輸出高比率の推移 | p363 | |
| 総理大臣賞を受賞 | p363 | |
| 第4節 施設の拡充整備 | p364 | |
| 1. 生産設備の合理化・大型化 | p364 | |
| 工場別生産分野の確立 | p364 | |
| 積極的設備投資 | p365 | |
| 生産能力の増大 | p365 | |
| 2. 桜島工場 | p366 | |
| 新鋭大型工作機械の設置 | p366 | |
| 新防潮堤築造工事 | p367 | |
| 産業機械・鉄構生産設備の新増設 | p367 | |
| ディーゼル機関生産設備の増設 | p369 | |
| 3. 築港工場 | p396 | |
| 修繕船設備の増強 | p369 | |
| 鋳鍛造設備の合理化 | p370 | |
| 4. 因島工場 | p371 | |
| 船台の拡張 | p371 | |
| 大型クレーンの設置と運搬設備の整備 | p371 | |
| 内業工場の自動化・効率化 | p372 | |
| 大型曳船北斗丸の配備 | p374 | |
| 5. 向島工場 | p374 | |
| 中小型船建造のモデル工場 | p374 | |
| 新造船・修繕船設備の整備拡充 | p376 | |
| 鉄構生産設備の整備 | p376 | |
| 6. 神奈川工場 | p376 | |
| 戦後初の4万重量トンドックの建設 | p376 | |
| 水中翼船建造工場の新設 | p377 | |
| 御召艇の改造と建造 | p378 | |
| 陸機工事の本格化と設備拡充 | p378 | |
| 7. 国内営業所・出張所 | p380 | |
| 東京支社 | p380 | |
| 九州営業所 | p380 | |
| 名古屋営業所 | p380 | |
| 横浜・札幌出張所 | p381 | |
| 第5節 研究・技術の強化 | p381 | |
| 1. 技術研究 | p381 | |
| 主力製品基礎固めの研究 | p381 | |
| 研究分野の拡大 | p382 | |
| 研究設備の充実 | p384 | |
| 2. 技術向上の奨励 | p384 | |
| 技術向上推進運動 | p384 | |
| 提案制度の実施 | p385 | |
| 発明考案巡回展示会の開催 | p385 | |
| 技術図書館の設立 | p385 | |
| 3. 生産性の向上対策 | p386 | |
| 社内技術規格の整備 | p386 | |
| 計量管理の強化 | p386 | |
| 第6節 人事・労務施策の充実 | p387 | |
| 1. 能力主義を指向 | p387 | |
| 人事管理基本方針の設定 | p387 | |
| 従業員数の推移 | p388 | |
| 現業管理組織の合理化 | p388 | |
| 資格制度の発足 | p389 | |
| 各層教育訓練の推進 | p390 | |
| 2. 新しい労使関係の形成 | p391 | |
| 社員組合連合会の結成と労使基本協定の締結 | p391 | |
| 労働組合の長期争議と労使関係の正常化 | p392 | |
| 話し合いの経営を推進 | p393 | |
| 実働7時間制の実施 | p393 | |
| 定年記念旅行制度と退職年金制度 | p394 | |
| 安全即生産の実践 | p394 | |
| 明るく健康な職場づくり | p395 | |
| 家族ぐるみの災害・疾病撲滅運動 | p395 | |
| MRA小集団活動の育成 | p396 | |
| 社内報活動の充実 | p397 | |
| 3. 福利厚生の充実 | p397 | |
| 健康管理体制の確立 | p397 | |
| 従業員の財産形成を促進 | p398 | |
| (持ち家の推進) | p398 | |
| (社内預金制度の発足) | p399 | |
| 共済会制度の発足 | p399 | |
| 第7節 経営管理業務の近代化 | p400 | |
| 1. 経理・資材管理体制の確立 | p400 | |
| 経理制度の変遷 | p400 | |
| (経理規程の制定) | p400 | |
| (原価計算基準の制定) | p400 | |
| (収益管理の充実) | p401 | |
| 資材管理の強化 | p402 | |
| 場内請負・外注管理体制の整備 | p403 | |
| 2. 近代的事務管理の推進 | p404 | |
| 事務管理能率促進運動 | p404 | |
| 事務の機械化 | p405 | |
| 第8節 社会とともに | p405 | |
| 使節団・調査団への参加 | p405 | |
| 経済諸団体活動 | p406 | |
| 関西石油株式会社の設立に協力 | p407 | |
| 外国貴賓・視察団の来訪相次ぐ | p409 | |
| 海外向けPR誌の発行 | p409 | |
| 共産圏諸国の見本市に出展 | p410 | |
| 第9節 記念行事、記念事業 | p411 | |
| 創業75周年記念 | p411 | |
| 創業80周年記念 | p412 | |
| 第4章 永田社長時代の経営 その1(昭和37年から昭和50年まで) ―百万人経営の展開期― | p417 | |
| 第1節 経営環境の国際化 | p417 | |
| 1. 日本経済の発展 | p417 | |
| 開放経済体制へ | p417 | |
| ニクソンショックと円変動相場制 | p418 | |
| 2. 造船業界の躍進 | p420 | |
| 第2次輸出船ブーム | p420 | |
| 造船企業の合併と系列化 | p420 | |
| 海運業界の企業集約 | p421 | |
| 第3次輸出船ブーム | p422 | |
| 新鋭大型工場の建設 | p423 | |
| 企業の海外進出 | p424 | |
| 外貨建て債権2兆円と為替差損 | p425 | |
| 史上空前の造船ブーム | p426 | |
| 第2節 新体制による経営 | p426 | |
| 1. 松原会長・永田社長体制 | p426 | |
| 総合国際企業へ | p426 | |
| 「百万人の経営」を提唱 | p427 | |
| 2. 「百万人の経営」を推進 | p428 | |
| 経営参画諸制度の整備 | p428 | |
| 労使協議制と労働組合の経営参画 | p429 | |
| 地域社会との対話と公益事業の推進 | p430 | |
| 福祉社会建設の提言と関西産業労使会議 | p431 | |
| 3. 経営組織の強化 | p432 | |
| 事業部制の実施 | p432 | |
| ブレーンスタッフの充実 | p433 | |
| 管理部門の強化 | p433 | |
| 4. 新時代の始動 | p434 | |
| 能力主義を基調とする人事能力開発制度の導入 | p434 | |
| 長期計画・中期計画の策定 | p434 | |
| 社員・工員の名称廃止 | p435 | |
| 経費節減運動の展開 | p436 | |
| 5. 舞鶴重工業株式会社の再建と合併 | p436 | |
| 舞鶴重工業の再建 | p436 | |
| 舞鶴重工業の再再建と当社との合併 | p438 | |
| 第3節 総合国際企業への道 | p439 | |
| 1. 国際競争力の強化 | p439 | |
| 適正操業の推進 | p439 | |
| 組織の拡充並びに動態化 | p440 | |
| 日立コミッティ、川崎重工業・日立造船委員会の発足 | p442 | |
| 経営効率化の推進 | p443 | |
| 複数副社長制と経営会議 | p444 | |
| 2. 超大型造船所の建設 | p445 | |
| 有明工場の建設を決意 | p445 | |
| シンガポールに進出 | p447 | |
| (海外事業の開始) | p447 | |
| (超大型船修繕基地に) | p447 | |
| 3. 営業活動の国際的展開 | p448 | |
| エンジニアリング体制の確立 | p448 | |
| 海外営業網の充実 | p449 | |
| 国際協力と国際分業 | p450 | |
| 4. ニクソンショックに耐える | p452 | |
| 円の切り上げ及び変動相場制の対策 | p452 | |
| 国際的経営の展開 | p453 | |
| (最適経営の推進) | p453 | |
| (国際金融体制の整備) | p454 | |
| (資材の国際調達) | p454 | |
| (合弁会社の設立) | p454 | |
| (国際ビジネスマンの養成) | p454 | |
| 5. 外資の導入、資本の増加 | p455 | |
| 最初の外資導入 | p455 | |
| 増資 | p455 | |
| 時価転換社債の発行 | p455 | |
| 第4節 受注と生産 | p457 | |
| 船舶部門 | p457 | |
| 1. 伸長著しい新造船 | p457 | |
| 拡大する輸出船市場 | p457 | |
| 建造記録の更新 | p458 | |
| VLCC、ULCCの出現 | p460 | |
| 計画造船受注の推移 | p461 | |
| 実を結んだ日中友好の船 | p463 | |
| 同型船の連続建造 | p467 | |
| (標準船型) | p467 | |
| (同一船型の連続建造) | p469 | |
| 2. 各種船舶の建造 | p469 | |
| 艦艇 | p469 | |
| (防衛庁向け) | p469 | |
| (海上保安庁向け) | p470 | |
| (測量船昭洋) | p471 | |
| (高速艇) | p471 | |
| 貨物船 | p471 | |
| (中速貨物船) | p471 | |
| (高速貨物船) | p471 | |
| (コンテナ船) | p472 | |
| 各種専用船 | p473 | |
| (タンカー) | p473 | |
| (撤積運搬船) | p473 | |
| (兼用船) | p475 | |
| その他の専用船 | p476 | |
| (LPG船・LNG船) | p476 | |
| (木材・チップ運搬船) | p477 | |
| (重量物運搬船) | p477 | |
| (自動車運搬船) | p477 | |
| 客船 | p478 | |
| 漁船 | p479 | |
| 浚渫船 | p480 | |
| 超自動化船 | p480 | |
| 3. 修繕船 | p482 | |
| 更新する修繕記録 | p482 | |
| 海外ネットワークの整備とアフターサービス体制の強化 | p482 | |
| 改造・海難工事 | p483 | |
| (船体大型化工事) | p483 | |
| (船種変更工事) | p484 | |
| (海難工事) | p485 | |
| 4. 海洋開発事業の開始 | p485 | |
| 陸機部門 | p487 | |
| 1. 陸機部門の進展 | p487 | |
| 陸機輸出の増加 | p487 | |
| 環境開発分野の発展 | p488 | |
| 2. 産業機械・原動機 | p489 | |
| 製鉄機械 | p489 | |
| (焼結設備) | p490 | |
| (ペレタイジング設備) | p490 | |
| (連続鋳造設備) | p490 | |
| (圧延設備) | p492 | |
| 鍛圧機械 | p492 | |
| (機械プレス) | p492 | |
| (3次元トランスファプレス) | p493 | |
| (液圧プレス) | p493 | |
| シールド掘進機 | p494 | |
| 荷役運搬機械 | p494 | |
| 軽機械 | p495 | |
| (食品機械) | p495 | |
| (プラスチック機械) | p495 | |
| 鋳鍛造品 | p496 | |
| HZ合金 | p497 | |
| 原動機 | p498 | |
| (ディーゼル機関) | p498 | |
| (タービン機関) | p499 | |
| (ボイラ) | p500 | |
| 3. プラント | p501 | |
| 砂糖プラント | p501 | |
| パルプ・製紙プラント | p501 | |
| (紙パルプ製造装置) | p501 | |
| (抄紙機設備) | p503 | |
| 化学肥料プラント | p503 | |
| 一般化学プラント | p504 | |
| (無機化学プラント) | p504 | |
| (都市ガスプラント) | p505 | |
| (油脂化学プラント) | p506 | |
| 石油化学プラント | p506 | |
| 石油精製プラント | p508 | |
| 圧力容器・熱交換器・加熱炉 | p508 | |
| 遠心分離機・撹拌槽・養生缶・晶析装置 | p511 | |
| 造水装置 | p512 | |
| 4. 鉄鋼構造物 | p513 | |
| 橋梁 | p513 | |
| (長大橋) | p513 | |
| (斜張橋) | p514 | |
| (高速道路橋) | p514 | |
| (本四連絡橋・その他) | p514 | |
| 水門 | p516 | |
| 水圧鉄管・水道鋼管 | p517 | |
| 超高煙突 | p518 | |
| 鉄骨・各種タンク | p519 | |
| 5. 環境装置 | p521 | |
| 地域冷暖房設備 | p521 | |
| 都市ごみ焼却施設 | p522 | |
| 廃水処理装置 | p523 | |
| 都市・産業廃棄物処理装置 | p524 | |
| 排ガス処理装置 | p526 | |
| (グランドフレア) | p526 | |
| (排煙脱硝装置) | p526 | |
| (都市ごみ焼却炉用塩化水素除去装置) | p527 | |
| 第5節 施設の拡充 | p528 | |
| 1. 設備の近代化 | p528 | |
| 船舶・陸機生産設備の強化 | p528 | |
| 生産能力の増大 | p529 | |
| 工場環境保全対策の推進 | p529 | |
| 2. 堺工場の建設と拡充 | p530 | |
| 大型船の建造工場 | p530 | |
| 総力を堺に | p532 | |
| 操業開始と竣工 | p533 | |
| 造船作業の数値制御化(ハイザックシステム) | p534 | |
| 正常化対策とその後の発展 | p535 | |
| 大型船修繕工事の開始 | p536 | |
| 3分割建造の開始 | p536 | |
| 有明工場のマザーヤードとして | p537 | |
| 3. 桜島工場 | p538 | |
| 船台・ドックの閉鎖 | p538 | |
| 陸機専門工場に転換 | p539 | |
| 重機械生産設備の増強 | p540 | |
| 大型原動機生産設備 | p541 | |
| 大型厚肉容器生産体制 | p541 | |
| 鉄構工場の合理化 | p542 | |
| 4. 築港工場 | p543 | |
| 修繕船大型化対策 | p543 | |
| 鋳鍛造設備の増強・合理化 | p544 | |
| 5. 因島工場 | p544 | |
| 新造船設備の合理化・拡充 | p544 | |
| 修繕ドックの建設 | p546 | |
| 陸機生産設備の増強 | p546 | |
| 6. 向島工場 | p548 | |
| 中型船建造設備の整備 | p548 | |
| 大型修繕船対策 | p549 | |
| 東工場を鉄構専門工場に転換 | p550 | |
| 7. 神奈川工場 | p552 | |
| 修繕船設備の増強 | p552 | |
| 陸機生産設備の増強 | p552 | |
| 本館の建設 | p554 | |
| 8. 舞鶴工場 | p554 | |
| 舞鶴造船所小史 | p554 | |
| 舞鶴歴史館の設置 | p556 | |
| 船舶・陸機設備の整備・増強 | p558 | |
| 西工場軽機械体制の整備 | p559 | |
| 電気計装制御機器の事業化 | p559 | |
| 9. 本社・支社・営業所 | p560 | |
| 本社社屋ビルの建設 | p560 | |
| 東京支社、パレスサイドビルへ移転 | p560 | |
| 陸機設計所の新築 | p560 | |
| 国内営業所 | p561 | |
| 第6節 新鋭有明工場の建設 | p562 | |
| 1. 理想の造船所を目指して | p562 | |
| 工場計画と建設工事の開始 | p562 | |
| 森の中の造船所を標榜 | p564 | |
| 2. 生産性が高く柔軟性に富んだ生産システム・設備 | p565 | |
| ハイカス(HICAS)の適用 | p565 | |
| 高生産性を追求した生産システム・管理方式 | p566 | |
| 最新鋭の生産設備 | p567 | |
| 総組工法と700トンガントリークレーン | p568 | |
| 2ドック5ステージ建造 | p568 | |
| 3. 地域社会・自然との調和 | p569 | |
| 外注工場対策 | p569 | |
| 周辺施設の整備 | p571 | |
| 地域社会とともに工場の竣工を祝う | p571 | |
| 第7節 研究・開発の促進 | p574 | |
| 1. 技術研究・開発 | p574 | |
| 研究・開発組織の拡充 | p574 | |
| 自主技術の開発を志向 | p575 | |
| 研究・開発の多角化 | p577 | |
| 開発モニター制度の発足 | p579 | |
| 研究設備の整備 | p579 | |
| 明石船型研究所の設立 | p580 | |
| 2. 技術管理の強化 | p581 | |
| 作業研究会活動の充実 | p581 | |
| 技術政策会議の設置と技術政策委員会の発足 | p583 | |
| 特許管理の強化 | p583 | |
| 技術情報管理の推進 | p584 | |
| 電算化の推進 | p585 | |
| 事故防止の推進 | p586 | |
| IEの全社的展開 | p587 | |
| 全員参加運動 | p587 | |
| 技能向上の全社的推進 | p588 | |
| 第8節 人事労務施策の進展 | p590 | |
| 1. 能力主義を基調とする人事諸制度の確立 | p590 | |
| 従業員の状況 | p590 | |
| 自己申告制度の採用 | p591 | |
| 事務論文制度の発足 | p591 | |
| 専門職員の育成 | p591 | |
| 職能管理制度の発足―「職務」と「能力」を重視 | p592 | |
| 能力開発の推進 | p593 | |
| 2. 全員参加の経営の推進と福祉の向上 | p596 | |
| 経営参加を軸とした新労働協約の締結 | p596 | |
| 58歳定年の実施 | p597 | |
| 週休2日制の実施 | p598 | |
| 労使一体となって無災害職場の建設を推進 | p598 | |
| 従業員の福祉向上を目指して | p600 | |
| 第9節 関連工業との連携、関係会社の育成 | p602 | |
| 1. 産業の核として | p602 | |
| 関連工業との連携強化 | p602 | |
| 場外・場内協力会社との連携 | p602 | |
| 2. 関係会社の育成 | p605 | |
| 分離独立したもの | p605 | |
| 〔日立造船不動産株式会社〕 | p605 | |
| 〔サービス3社(関西サービス、日神サービス、日立造船中国工事)〕 | p606 | |
| 〔日立造船産業株式会社〕 | p606 | |
| 新分野に進出したもの | p608 | |
| (瀬戸内海タンククリーニング株式会社) | p608 | |
| (日立造船非破壊検査株式会社) | p608 | |
| 経営を受託したもの | p609 | |
| (大昌産業株式会社) | p609 | |
| (三和工業株式会社) | p609 | |
| (日立造船富岡機械株式会社) | p609 | |
| (丸善ガス開発株式会社) | p610 | |
| (福井機械株式会社) | p611 | |
| (東洋運搬機株式会社) | p611 | |
| (日立造船臨海工事株式会社) | p613 | |
| (大機ゴム工業株式会社) | p613 | |
| (内海造船株式会社) | p614 | |
| (日産建設株式会社) | p616 | |
| 第10節 社会とともに | p617 | |
| 海外視察団・使節団に参加 | p617 | |
| 経済団体活動 | p618 | |
| 日本万国博覧会への参加 | p620 | |
| 外国貴賓・視察団の来訪 | p621 | |
| パブリシティ活動の積極化 | p621 | |
| 地域社会とのコミュニティづくり | p623 | |
| (地域奉仕) | p623 | |
| (盆踊り大会) | p624 | |
| 第11節 行事 | p625 | |
| 創業85周年・90周年 | p625 | |
| 松原相談役の社葬 | p626 | |
| 第5章 永田社長時代の経営 その2(昭和50年から昭和54年まで) ―構造転換期における百万人の経営の展開― | p627 | |
| 第1節 激動する経済環境 | p627 | |
| 1. 高度経済成長時代の終焉と産業構造の変化 | p627 | |
| 低成長経済の定着化と産業構造の変化 | p627 | |
| 重化学工業の衰微と民間設備投資の減少 | p628 | |
| 重層構造の形成と構造不況業種 | p629 | |
| 2. 戦後最悪の不況克服を図る造船業界 | p629 | |
| 契約キャンセル、船種変更の続出 | p629 | |
| 日本造船工業会の不況対策 | p630 | |
| 不況対策立法 | p632 | |
| 造船不況カルテルと設備削減 | p633 | |
| 第2節 戦略経営の展開 | p635 | |
| 1. 造船の構造不況に対処 | p635 | |
| 50・51年度危機突破対策の実施 | p635 | |
| 「戦略生産」の推進 | p637 | |
| 2. 組織機構の強化と経営の効率化 | p637 | |
| 海外法人企業の設立 | p637 | |
| 国内営業網の充実―全国的営業拠点づくり | p639 | |
| 事業部制の廃止、企画機能充実のための調査役の設置 | p639 | |
| K作戦の展開 | p640 | |
| 3. 労使一体となって事業構造転換計画を推進 | p641 | |
| 事業構造転換労使経営専門委員会の設置 | p641 | |
| 既存工場の統合計画の策定 | p642 | |
| 工場別の新造船設備の処理と転用計画 | p643 | |
| 陸機部門の生産体制の整備 | p643 | |
| 職域経審の推進 | p644 | |
| 4. 減量経営の実施 | p645 | |
| 新規学卒者採用の中止 | p645 | |
| 残業ゼロ体制の実施 | p645 | |
| 技能職員他社派遣の実施 | p646 | |
| 雇用対策の実施 | p647 | |
| 労働組合、ベースアップの要求取り下げ | p648 | |
| (付)組合の組織統一 | p649 | |
| 5. 全員精鋭化教育の推進 | p650 | |
| 教育推進本部の設置 | p650 | |
| 全員精鋭化教育の実施 | p651 | |
| 6. 陸機部門の拡大策の実施 | p653 | |
| 陸機事業拡大委員会(LEC)の設置 | p653 | |
| 有明に新鋭陸機工場建設 | p653 | |
| 戦略管理マップ(13システム58ユニット) | p654 | |
| 7. 海洋分野へ新展開 | p656 | |
| 海洋営業本部の発足 | p656 | |
| 総合力で新分野を開拓 | p657 | |
| 8. 優先株・外債の発行 | p657 | |
| 第1回優先株式の発行 | p657 | |
| 外債の発行 | p658 | |
| 連結財務諸表制度の実施 | p659 | |
| 9. 関係会社対策 | p660 | |
| 自主経営力の強化と協力会社の効率化 | p660 | |
| 事業分野拡大のための関係会社の新設 | p661 | |
| (分離独立会社) | p661 | |
| (新分野進出会社) | p662 | |
| (系列化) | p662 | |
| (その他) | p662 | |
| 第3節 受注と生産 | p663 | |
| 1. 新造船部門 | p663 | |
| 深刻な需給アンバランスとキャンセル・船種変更 | p663 | |
| 厳しい状況下で市場開拓 | p664 | |
| ばら積船・80型タンカーから受注回復 | p664 | |
| 建造実績 | p665 | |
| (タンカー・ばら積船) | p665 | |
| (貨物船) | p666 | |
| (自動車運搬船) | p667 | |
| (冷凍船・漁業取締船・補給兼診療船) | p667 | |
| (艦艇) | p668 | |
| (客船・フェリー) | p668 | |
| 2. 改修船部門 | p669 | |
| 改造船計画部・船舶技術サービスセンターの設置 | p669 | |
| タービンからディーゼルへ主機換装工事の需要増大 | p669 | |
| 船体延長工事・船種変更改造工事・IMCO関連工事で受注拡大 | p670 | |
| 3. 海洋部門 | p672 | |
| 3年で1,000億円事業へ急成長 | p672 | |
| 4. 陸機部門 | p673 | |
| 海外向け大型プロジェクトの受注に努力 | p673 | |
| 関係会社を含めた受注体制の強化 | p673 | |
| 産業機械 | p674 | |
| (製鉄機械) | p674 | |
| (プレス) | p675 | |
| (原動機) | p676 | |
| (ボイラ) | p678 | |
| (建設機械) | p678 | |
| (セメント機械) | p679 | |
| プラント | p679 | |
| (肥料プラント) | p679 | |
| (一般化学・石油化学プラント) | p680 | |
| (砂糖プラント) | p681 | |
| (紙・パルププラント) | p681 | |
| (造水装置) | p682 | |
| (単体機器) | p683 | |
| 鉄鋼構造物 | p684 | |
| (橋梁) | p684 | |
| (水門) | p684 | |
| (水圧鉄管・水道鋼管) | p685 | |
| (超高煙突・鉄骨) | p685 | |
| (タンク・サイロ) | p686 | |
| 環境装置 | p686 | |
| (都市ごみ焼却施設) | p686 | |
| (地域冷暖房設備) | p687 | |
| (産業廃棄物処理装置・廃水処理設備) | p687 | |
| 第4節 新製品・新技術の開発 | p688 | |
| 1. 自社開発 | p688 | |
| HZノズル | p688 | |
| 日立B&Wツインバンク機関 | p688 | |
| 炉頂圧タービン発電装置 | p689 | |
| ジャッキアップ式オイルリグ | p690 | |
| ヒートポンプ | p690 | |
| 廃棄物熱分解ガス化発電システム | p690 | |
| ロータリープレス | p691 | |
| NOXNON500・NOXNON600排煙脱硝装置用触媒 | p691 | |
| 船舶自動航法装置(トランソライン) | p692 | |
| 都市ごみ高速コンポスト化装置 | p692 | |
| 2. 技術提携 | p693 | |
| 省エネルギー・新エネルギー時代への対応 | p693 | |
| 〔ブリヂストン液化ガス社のLPG陸上基地〕 | p693 | |
| 〔シュタインミュラー社の自然循環水管ボイラ(陸用)〕 | p693 | |
| 〔バブコックパワー社の石炭焚き舶用ボイラ〕 | p693 | |
| 〔フォーゲルブッシュ社のケーンパワーアルコールプラント〕 | p693 | |
| 〔コンバッションシステムズ社の流動燃焼式焼却装置〕 | p694 | |
| 〔エフエムシー社の乾燥機〕 | p694 | |
| 〔テクノタームシステムズ社のヒートポンプ〕 | p694 | |
| 要素技術の充足 | p694 | |
| 〔キューンレコップカウシュ社の大型送風機〕 | p694 | |
| 〔フォスターウィラー社の湿式冷却塔〕 | p694 | |
| 〔エコダイン社の乾式冷却塔〕 | p695 | |
| 〔ジョンヘスティ社の舵取機とデッカ社のオートパイロット〕 | p695 | |
| 〔マンネスマンデマーグ社のコンプレッサー〕 | p695 | |
| 〔ゼネラルエレクトリック社の蒸気タービン、スタールラバル社・GM社のガスタービン〕 | p695 | |
| 中近東地区の造水装置のニーズに対応 | p696 | |
| 3. 技術輸出 | p696 | |
| ブラジル・CCN社への技術協力 | p696 | |
| 中国・大連造船所への技術協力 | p697 | |
| グランドフレアの輸出 | p697 | |
| 第5節 社会活動 | p698 | |
| 1. 広報活動の強化 | p698 | |
| 海外見本市参加 | p698 | |
| 国内展 | p699 | |
| 新PR誌の作成 | p699 | |
| 2. 経済団体活動への参加 | p700 | |
| 日本経営者団体連盟 | p700 | |
| 日本経営協会 | p701 | |
| 関西経営者協会 | p701 | |
| 日本在外企業協会 | p702 | |
| 3. その他の団体活動 | p703 | |
| みどり会と沖縄国際海洋博・神戸博への参加 | p703 | |
| 春光会・日産懇談会 | p704 | |
| 第6章 木下社長時代の経営(昭和54年から昭和56年3月まで) ―創業第2世紀へ向けて― | p707 | |
| 第1節 国際化を進める日本経済 | p707 | |
| 1. 2度にわたる石油危機を克服 | p707 | |
| 2. 貿易摩擦と新しい技術革新の進行 | p708 | |
| 第2節 第4・第5の柱の確立を目指して | p709 | |
| 1. 永田会長・木下社長体制 | p709 | |
| 2. カンパニープロジェクトの設定 | p711 | |
| 設定の経緯 | p711 | |
| ねらいとその特徴 | p711 | |
| 推進状況 | p712 | |
| 3. 強靭な経営体質づくりを目指す―中期経営計画の策定 | p713 | |
| 4. メカトロニクス技術の発展と生産性向上、製品競争力の強化 | p714 | |
| 5. 地縁技術の提唱 | p715 | |
| 6. 海洋分野の発展を支える生産技術開発 | p715 | |
| 7. 技能向上の気風を醸成する「工師」制度 | p716 | |
| 8. ZD実施賞の受賞 | p717 | |
| 第3節 海外との交流 | p718 | |
| 1. 華国鋒中国総理を迎える | p718 | |
| 2. 湯口副社長、中国船舶工業公司顧問に | p718 | |
| 3. 石灰焚き船国際会議に出席 | p719 | |
| 4. 訪米ZD視察交流団に参加 | p720 | |
| 5. 海外研修生の受け入れ | p721 | |
| 第4節 創業100周年記念式典 | p722 | |
| 1. 100周年記念式典を挙行 | p722 | |
| 2. 会長挨拶 | p723 | |
| 口絵 | p723 | |
| 資料 | p725 | |
| 事業内容 | p727 | |
| 国内事業所 | p728 | |
| 海外事務所及び海外関係会社 | p729 | |
| 関係会社 | p730 | |
| 歴代役員 | p734 | |
| 工場の変遷 | p736 | |
| 社章の変遷 | p738 | |
| 組織の変遷 | p738 | |
| 財務・業績の推移 | p744 | |
| 株価・株主数の推移 | p746 | |
| 事業所別設備投資額の推移 | p747 | |
| 部門別設備投資額の推移 | p747 | |
| 受注高の推移 | p748 | |
| 受注残高の推移 | p749 | |
| 売上高・輸出高の推移 | p750 | |
| 従業員数の推移 | p751 | |
| 原始定款 | p754 | |
| 歴代経営者の面影 | p756 | |
| 年表 | p761 | |
| あとがき | NP |
- 索引リスト
-