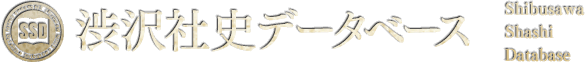※ (グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 慶長10年(1605) | - | 幕命により英人ウイリアム・アダムス八〇噸及び一〇〇噸帆船を建造 本邦に於ける西洋型帆船の濫觴である 内一隻「サンブエナベンソーラ」はメキシコへ航す | 参考事項 |
| 慶長14年(1609) | 9月 | 幕府豊臣氏に対する政略上西国諸大名の五〇〇石積以上の兵船製造を禁止す | 参考事項 |
| 慶長18年(1613) | - | 仙台藩主伊達政宗 江戸船手頭向井将監忠勝と謀り、幕府の船大工を借入れ西洋型帆船を建造(長一八間 幅五間半 高一四間一尺 一八〇人搭載)尚建造に当つて西班牙僧ルイス・ソテロ援助す 家臣支倉六右衛門外メキシコへ航す | 参考事項 |
| 元和4年(1618) | 2月 | 向井将監忠勝に相州三崎造船検査を命ず | 参考事項 |
| 寛永12年(1635) | - | 「鎖国令」を発布し 海外航行を禁ず//五〇〇石以上の船舶を没収し同時にその新造船を禁止す 又二本檣を禁じ一本檣となし、且つ船底竜骨の使用を禁ず | 参考事項 |
| 寛永13年(1636) | 5月 | 商船の外航を禁ず | 参考事項 |
| 寛永15年(1638) | 5月 | 五〇〇石積以上の商船製造を許可す | 参考事項 |
| 承応元年(1652) | 8月 | 「海航法度」を令す | 参考事項 |
| 寛文9年(1669) | 12月 | 長崎代官末次平蔵 和蘭船を模造す(長一五間 幅三間三尺一寸 深八尺一寸 櫓六〇立五〇〇石積)一〇年三月竣工、同月一六日長崎発、四月一〇日品川着 | 参考事項 |
| 天明6年(1786) | - | 大串六郎平幕命により大阪に於て「三国丸」(長九〇尺 幅二四尺 深九尺 容積一五〇〇石)を建造(外型日本型、船底中国装、帆蘭式二段桁) | 参考事項 |
| 寛政10年(1798) | - | 向井将監忠勝蘭船模擬の船を建造 本牧沖にて試乗 | 参考事項 |
| 天保2年(1831) | 4月 | 向井将監忠勝「天地丸」(長一五間 肩三間七寸二分 立足一間三寸二分 櫓七六挺立)を建造 | 参考事項 |
| 天保5年(1834) | - | 徳川斉昭 北地開拓の急務を唱え和蘭船に模して渡航のための大船建造を幕府に建議す、幕府許可せず | 参考事項 |
| - | 小普請向山篤、勝麟太郎等大船建造、海軍創設を建議す | 参考事項 | |
| 天保9年(1838) | 6月 | 水戸烈公軍艦「日立丸」(長二四間 幅三丈八尺七寸)を建造せんとしたが幕議これを許さず僅かに模型のみに止む 臣小納戸浅沼広寿、臣白復利和西洋戦式により木船一隻(長九尺調二尺五寸)を造る | 参考事項 |
| 12月 | 松本斗機蔵英船モリソン号につき上書す | 参考事項 | |
| 嘉永元年(1848) | - | 【渋沢栄一】このころ実名を美雄とする。後に伯父渋沢誠室の命名で栄一と改める。〔8歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
| - | 島津斉彬公蘭学者箕作阮甫をして「舶用蒸気機関書」を飜訳せしむ | 参考事項 | |
| 嘉永2年(1849) | 9月 | 「水蒸船略説」(蒸気機関書の訳本)成る | 参考事項 |
| 嘉永3年(1850) | - | 長州恵比寿鼻に於て「丙辰丸」(スクーナー木製 二檣 四七噸)を製造 | 参考事項 |
| 嘉永4年(1851) | 10月 | 薩州鹿児島磯竜洞院前海浜に於て西洋型帆船「以呂波丸」(三檣)を起工 | 参考事項 |