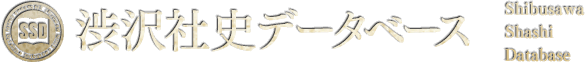※ (グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 安政元年(1854) | 7月21日 | 蘭船サラ・リデイア号長崎入港、幕府の軍艦註文約定に対し東印度総督の来訓を伝う | 参考事項 |
| 7月 | 薩州有村に於て幕府用として「大元丸」(二四間 安政二年一一月竣工)、藩用として「承天丸」(二四間 安政二年月不詳竣工)を起工//又牛根に於て幕府用として「鳳瑞丸」(二〇間 安政二年三月進水 九月竣工)、藩用として「万年丸」(二〇間 安政二年四月進水)を起工 | 参考事項 | |
| 8月31日 | 蘭船スームビング号長崎入港、滞留中(三月間)艦長海軍中佐フアビユス操船術につき教育を諾す | 参考事項 | |
| 11月4日 | 豆相駿地震災のため下田港に滞泊中の魯国軍艦フレガットデイヤナ号暗礁に触れ、補修のため戸田浦へ回航中駿州宮島村沖で浸水沈没(一二月二日)後魯国人戸田に於てシコナ号以下六隻を建造「君沢形」と称す | 参考事項 | |
| 12月 | 佐賀藩三重津御船屋脇に造船所を設置 | 参考事項 | |
| 安政2年(1855) | 3月23日 | 戸田村で新造のシコナ号にプーチヤチン始め一〇〇人乗組みカムチヤツカへ向け出港 | 参考事項 |
| 7月29日 | 海軍興立の議決定し勝麟太郎外各員へ伝習万申渡さる | 参考事項 | |
| 7月 | 長崎製鉄所建設の議起り「大船製造掛」を設く | 重要事項 | |
| 7月 | 和蘭フアビユス海軍中佐ゲデー号に搭乗スームビング号とともに来朝(スームビング艦長ペルスライケン大尉以下二二名派遣教師搭乗) | 参考事項 | |
| 8月13日 | 薩藩「昇平丸」を幕府に上納、幕府「昌平丸」と称す | 参考事項 | |
| 8月 | 和蘭スームビング号(一八五〇年 和蘭フレッシング建造 蒸汽外車 砲六門 一五〇馬力 長二九間 幅五間 深四間 約二五〇噸 後に「観光」と称す)を幕府に献上 | 参考事項 | |
| 8月 | 薩藩江戸に於て蒸汽機関を越通船に装備した「雲行丸」を竣工 | 参考事項 | |
| 9月1日 | 海軍伝習生矢田堀影蔵外三名昌平丸にて長崎へ赴く(尾形作右衛門外一六名陸行) | 参考事項 | |
| 10月20日 | 海軍伝習生長崎到着 海軍伝習開始 教場 長崎西奉行所 | 参考事項 | |
| 11月15日 | フアビユス海軍中佐ゲデー号に搭乗長崎を去る ペルスライケン大尉長崎海軍伝習所教育班長となる | 参考事項 | |
| 11月 | 海軍伝習方総取締永井玄蕃頭 和蘭商人ハートウエンを介し長崎熔鉄所用蒸気機械場釜、鎔鉄炉附属蒸気機械類並びに鉄槌等代凡壱万金程の購入を依頼 | 重要事項 | |
| 安政3年(1856) | - | 【渋沢栄一】父の代理で領主安部摂津守の岡部の陣屋で用金の命を受ける。代官が傲慢で栄一を侮蔑、圧制に痛憤し封建の弊に強烈な反感を持つ。〔16歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月 | 江戸石川島に於て水戸斉昭督工の下に「旭日丸」(船型ハルク 長二三間一尺 幅五間二尺 深四間)を起工(五月竣工七月故障あり 試運転済 安政四年俗に「厄介丸」と称す) | 参考事項 | |
| 1月 | 長崎海軍伝習方総取締永井岩之亟伝習所に於ける造船術習得のため カッター船(一檣)建造につき幕議へ伺出 | 参考事項 | |
| 2月 | カッター船の建造を許可 | 参考事項 | |
| 2月 | 幕府戸田村に於て米国式の「韮山形」と称する端舟数隻を建造 | 参考事項 |