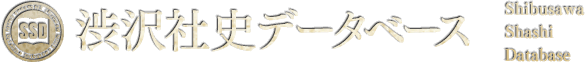全1631件中20件 1421件〜1440件目を表示
| 会社名 | 業種 | 社史タイトル(出版年) | 会社沿革と社史メモ |
|---|---|---|---|
| 丸善(株) | 小売業 | 『丸善百年史 : 日本近代化のあゆみと共に. 上巻』(1980.09) | 明治維新期に西洋諸国の科学・技術・文化を導入すべく、福沢諭吉門下の早矢仕有的(はやし・ゆうてき、1837-1901)が洋書輸入を主とする貿易事業を始め、1869年(明2)横浜に丸屋商社(丸屋善八店)を創立。1880年(明13)株式組織に改組し丸善商社と改称、本店を東京へ移転。貿易商会や丸屋銀行を開設するが景気変動などで破綻。丸善商社は再建に奮闘し1893年(明26)丸善と改称する。以来洋書を中心とした衣料・雑貨などの輸入販売を通じ、欧米文化紹介の一翼を担う。100年史は日本文化の近代化の軌跡を辿る側面史を意図し、研究者が執筆。三分冊構成で、上巻は明治時代、下巻は大正から100周年までを記述、資料編巻頭には機関誌「学鐙」の表紙写真等を掲載している。[2008年大日本印刷の連結子会社となる] |
| 丸善(株) | 小売業 | 『丸善百年史 : 日本近代化のあゆみと共に. 下巻』(1981.12) | 『丸善百年史 : 日本近代化のあゆみと共に. 上巻』(社史ID:08240)の下巻 |
| 丸善(株) | 小売業 | 『丸善百年史. 資料編』(1981.12) | 『丸善百年史 : 日本近代化のあゆみと共に. 上巻』(社史ID:08240)の資料編 |
| 丸紅(株) | 商社 | 『丸紅前史』(1977.03) | 近江商人初代伊藤忠兵衛(1842-1903)は1858年(安政5)初めて大坂へ近江麻布行商に行く。1872年(明5)には関東織物も扱う呉服太物商の紅忠を大阪に開店、1884年(明17)に伊藤本店と改め、暖簾は丸に紅とした。貿易を目指し会社の制度を整え、2代忠兵衛(1886-1973)に引き継ぐ。1914年(大3)伊藤忠合名会社発足、1921年(大10)合併により丸紅商店となり、織物問屋として内外に積極経営を広げる。戦時下合併により三興、大建産業と社名変更するが、戦後1949年(昭24)分割により丸紅として再発足。1977年(昭52)刊の『前史』は創業から再発足までの沿革と資料で、1984年(昭59)の『本史』刊行時に復刻印刷版が出ている。 |
| 丸紅(株) | 商社 | 『丸紅本史 : 三十五年の歩み』(1984.12) | 1949年(昭24)大建産業は過度経済力集中排除法の適用により丸紅、伊藤忠商事、呉羽紡績、尼崎製釘所に分割。再発足した丸紅は日本経済の成長とともに総合商社として業容を拡大する。創業25周年記念事業で社史編纂が開始されるが、1976年(昭51)ロッキード事件が発生し、『前史』のみ刊行して作業凍結。その後の経営改革と体質強化の歩みも掲載した『本史』を1984年(昭59)に刊行。同時に『前史』を復刻印刷し、合わせて『丸紅社史』とした。 |
| 満州中央銀行 | 銀行 | 『満州中央銀行史 : 通貨・金融政策の軌跡』(1988.11) | 辛亥革命後の満州は軍閥割拠となり、幣制は紊乱状態であった。1931年(昭6)満州全土を占領した関東軍は翌1932年(昭7)満州国を建国。同年幣制を統一するため満州中央銀行法を公布、特殊会社として満州中央銀行を創立。旧貨幣を回収して金融機構を整備し産業開発を推進する。1945年(昭20)侵攻したソ連軍の命令により一切の営業を停止。本銀行史は『満州中央銀行十年史』(1942年刊)、中国経済接収責任者張公権の収集文書(フーバー研究所所蔵)、中国吉林省金融研究所『偽満州中央銀行史料』(1984年刊)等を元に旧職員らが執筆したもので、満州地域史の中での満州中央銀行の機能を記述。前史、草創、展開、終焉の4部と補論、統計資料、年表、写真等からなり、索引付。 |
| 満洲電業(株) | 電力 | 『満洲電業史』(1976.11) | |
| (株)マンダム | 化学工業 | 『マンダム五十年史』(1978.04) | |
| 三浦藤沢信用金庫 | 銀行 | 『三浦藤沢信用金庫60年史』(2011.07) | |
| (株)三重銀行 | 銀行 | 『Open up : 大いなる未来へ向けて : 三重銀行100年史』(1999.03) | 明治中期の四日市は貿易取扱高が中部地方最高のシェアを誇り、周辺には紡績、製糸、鉄工、製油、製紙などの本格的近代工場が稼動していた。第一国立銀行は名古屋よりも早く1884年(明17)四日市に支店を開設。地元有力者のなかから「四日市にも本店銀行を」との待望論が高まり、1895年(明28)に四日市の経済力の象徴として四日市銀行が設立され順調に成長する。頭取の贈収賄事件連座により1932年(昭7)より2年間休業、1939年(昭14)三重銀行と改称し再スタートを切る。100年史は明治の創業時から平成の新本店完成までの100余年の歩みを目で見る写真史として編集し、三重紡績の創設を援助した渋沢栄一についても掲載。資料編の年表は『三重銀行史』(1987年刊)掲載以降の1986年(昭61)より記述。 |
| 三重交通(株) | 鉄道・バス | 『三重交通50年のあゆみ』(1994.03) | 伊勢神宮参宮の街道が整備されていた三重県では、明治期に鉄道網が次々発達。バス事業も広がる中で1931年(昭6)伊勢電鉄自動車(後の神都交通)が創業。鉄道事業も行うが戦時下の経済統制で神都交通を中心に県下の鉄道5社自動車2社が合併し、1944年(昭19)三重交通が誕生。戦後は自動車時代の到来と共に事業も発展。1964年(昭39)鉄道事業を三重電気鉄道(翌年近畿日本鉄道に合併)へ譲渡、バス専業となる。観光や不動産事業にも進出し、三交グループを形成して発展する。50年史は現況のグラビア、歴史編、資料編からなり、歴史編序章に前身7社の略史を記載。本文は各テーマを見開き2ページに関連写真と共にまとめている。 |
| 三河セメント(株) | 窯業 | 『三河セメント社史』(1937.07) | 窯業を学んだ斎藤実堯(さいとう・さねたか、1844-1898)は石灰石の産地である愛知県田原町で、県令の斡旋により藩士授産事業として1882年(明15)東洋組を起こしセメント製造開始。東洋組を引継いだ実業家水谷孫左衛門(1850-1913)は事業を拡張し、1888年(明21)三河セメント会社として操業。しかし経営難で第一銀行四日市支店の担保となり、渋沢栄一の委嘱で1891年(明24)浅野セメント工場の委託経営とされ、三河セメント工場として営業。その後名古屋の実業家に譲渡され、1898年(明31)株式会社となる。当該社史では冒頭の特別篇でセメント発明の起源から日本におけるセメント工業の発達を概観。個人経営篇で東洋組から三河セメント工場までの沿革、会社篇で三河セメント(株)の40年の沿革を記述。[1940年(昭15)東海セメントと合併し東洋産業となる(現・太平洋セメント)] |
| 三木産業(株) | その他製造業 | 『出藍録 : 三木産業小誌』(1955.04) | 徳島の雑貨商三木家は1674年(延宝2)阿波藍の取扱を開始。後に江戸に支店を構え、明治期には印度藍やドイツ産人造藍を扱う。染料業界へ進出し、1918年(大7)三木与吉郎商店を継承して(株)三木商店創立。外地へも発展し1943年(昭18)三木産業(株)と改称。第二次大戦後は染料と化学製品を幅広く取扱う問屋として復興する。当該社史は三木家文書により研究者が執筆。藍商の創業から戦後の復興までの280年の歩みを簡潔に記し、(株)三木商店創立以降の詳細年譜、役員一覧等を付す。本文中に藍製造装置等の図版入り。 |
| (株)ミキモト | 小売業 | 『輝きの世紀 : 御木本真珠発明100周年記念』(1993.01) | 『御木本真珠発明100年史』(社史ID:08280)のビジュアル版 |
| (株)ミキモト | 小売業 | 『御木本真珠発明100年史』(1994.07) | 鳥羽出身の御木本幸吉(みきもと・こうきち、1858-1954)は海産物商の傍ら、乱獲されていた志摩の真珠貝を守るため真珠養殖を試みる。1893年(明26)半円真珠の養殖成功を機に御木本真珠養殖場を創設、本格的に事業化に乗り出す。1899年(明32)には東京・銀座に日本初の真珠専門店である御木本真珠店を開設。1949年(昭24)個人経営の養殖場と真珠店は、法人組織の御木本真珠と御木本真珠店に改組。その後1972年(昭47)両社の合併によって現在の(株)ミキモトとなる。100年史ではまず御木本100年の歩みとして御木本幸吉と一族について記述し、幸吉が実業界で最も兄事した渋沢栄一と森村市左衛門にも触れている。次に御木本グループのミキモト、ミキモト装身具、御木本製薬、御木本真珠島の4社についてそれぞれ沿革と資料・年表を掲載。100周年記念にビジュアル版社史『輝きの世紀』も出版。 |
| (株)御木本真珠島 | 小売業 | 『御木本真珠島40年の歩み : 開島40周年記念誌』(1991.07) | 御木本幸吉(みきもと・こうきち、1858-1954)は1893年(明26)鳥羽の相島で真珠養殖に成功。御木本真珠を創業し事業を広げると、真珠のふるさとの相島は内外に知られるようになる。幸吉は戦後復興期に真珠産業を世界に紹介するため、1951年(昭26)(有)御木本真珠ヶ島を設立、島を一般公開。1971年(昭46)(有)御木本真珠島に改称、1980年(昭55)株式会社となる。40年間に皇室や世界各国の要人を始め、国内外の一般観光客も4000万人近く訪れる観光地に成長する。40年史は「御木本幸吉と真珠島」「ロイヤルファミリーと真珠島」「真珠島40年の歩み」の構成で、多くの客人の写真を掲載している。 |
| みずほ証券(株) | 証券 | 『日本の証券市場の歩み : みずほ証券百周年記念』(2018.02) | |
| 三井 | 商社 | 『三井事業史. 資料篇 1』(1973.12) | 三井家の創業から第二次世界大戦後の財閥解体までの三井関係事業に関わる、江戸期ならびに明治期の制度や組織、財務に関わる重要資料を、選択的に収録した4巻5冊の資料篇。1は創業から文化・文政期まで、2は幕末維新期、3は1876年(明9)三井銀行の創立から1909年(明42)三井合名会社の設立まで、4上下は三井商店理事会と三井営業店重役会の議事録全文。資料は全て(財)三井文庫が所蔵するもので、配列は事項別作成年代順。各巻末に解題付。後に刊行された本篇3巻5冊と共に「三井事業史」を構成する。 |
| 三井 | 商社 | 『三井事業史. 資料篇 2』(1977.02) | 『三井事業史. 資料篇 1』(社史ID:07800)の2 |
| 三井 | 商社 | 『三井事業史. 資料篇 3』(1974.07) | 『三井事業史. 資料篇 1』(社史ID:07800)の3 |